■10月12~15日 横浜、總持寺「御両尊御征忌会(ごりょうそんごしょうきえ)」です。■
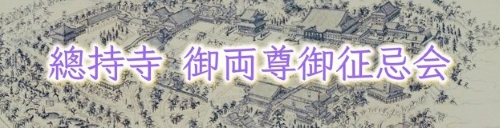
横浜市鶴見区の鶴見が丘にある「總持寺(そうじじ)」は、福井県「永平寺(えいへいじ)」と並ぶ曹洞宗大本山のひとつ。

曹洞宗では、釈迦の教えを日本に伝え、永平寺を開いた「道元禅師(どうげんぜんじ、「高祖」)」、總持寺を開いて全国に教えを広めた「瑩山禅師(けいざんぜんじ、「太祖」)」を「両祖(りょうそ)」と呼び、「釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)」とあわせて「一仏両祖(いちぶつりょうそ)」として祀ります。
はじめ、石川県の「諸嶽寺(もろおかでら)」を元亨元年(1321)太祖「瑩山」が「諸嶽山總持寺」と改めました。明治の焼失を機に横浜市に移転。開かれた禅苑として国際的な「禅の根本道場」となっています。

「道元」の教えを受け継いだ4代目「瑩山」は、文永5年(1268)現在の福井県武生市に誕生。父は越前・越後の豪族「瓜生氏(うりゅうし)」で、両親ともに信仰深く、母が観音さまに祈願をこめ、その霊験によってこの世に生を受けたといわれています。
8歳にして「永平寺」に登り、3代「徹通(てっつう)」に弟子入りしました。永平寺での修行は厳しくも鍛えられ、13歳の春に、2代目「懐弉(えじょう)」について得度を受け、18歳で諸国行脚、修行の旅に出ます。21歳の秋、永平寺の「徹通」のもとに戻った「瑩山」は、その翌年、「徹通」のお供として金沢の「大乗寺(だいじょうじ)」へ移ります。
修行7年の後、27歳にして公案「平常心是道(びょうじょうしんこれどう)」を聞き大悟して教えを体得、翌28歳の正月、徹通禅師の教えを継ぎました。徹通禅師を助けて布教活動に専念するうち35歳で大乗寺2世となり、45歳で能登に「永光寺(ようこうじ)」(石川県羽咋市)を開きます。
54歳の春、諸嶽寺の「定賢権律師(じょうげんごんのりっし)」の願いを受け入れ、寺に入って「總持寺」と改めます。翌年、「後醍醐天皇」より「曹洞宗出世道場」という額、そして紫衣を賜り「大本山」となりました。正中2年(1325)夏、病床に倒れた「瑩山」は、9月29日、58歳の生涯を閉じました。

總持寺の第2代住職「峨山(がさん)」は、建治元年(1275)能登国の瓜生田(うりゅうだ、現・津幡町)に生まれ、若くして比叡山に上り天台を学んだのち、「瑩山」に謁して禅の門に入り、瑩山より嗣法(しほう:師の仏法・法統を受け継ぐこと)しました。
正中元年(1324)瑩山より「總持寺」の住職を任せられ、暦応3年(1340)「永光寺」の住職を兼職することになりました。以来、貞治4年(1365)91歳で入寂するまで、20余年にわたって両寺を往還しながら全国に教えを広めました。人材育成に努め、五院・二十五哲の俊僧を輩出して「五院輪住(ごいんりんじゅう)」〔※〕の制度を定めるなど、教線拡大と末寺拡張の基盤を築きました。
「峨山」は、總持寺と永光寺の住職を兼任していたあいだ、毎日未明に永光寺の朝課を勤めたあと、約13里(約50km)の山道を超えて總持寺に赴き、朝の読経に間に合ったと伝わります。峨山が往復した道は「峨山道(がさんどう)」と呼ばれています。毎年、禅師の遺徳をしのんで「峨山道巡行」が行なわれます。
※五院輪住(ごいんりんじゅう):曹洞宗の住職には「独住(どくじゅう)」と「輪住(りんじゅう)」の2種類がある。「独住」は、期間に制限なく住職を務め、「輪住」は、短期間で住職が交替する。「輪番住職」の略語。輪住制度は、住職位をめぐる争いや門下の分裂を防いで合議体制を生み出す。第2代「峨山」のあと、5院の住職が順番に總持寺住職を務めた。明治3年(1870)まで約500年間、總持寺では「輪住制度」を維持していた。

大本山總持寺を開いた「瑩山禅師」、第2代「峨山禅師」を「御両尊(ごりょうそん)」と呼びます。10月12~15日の「御両尊御征忌会(ごりょうそんごしょうきえ)」にて、御両尊の遺徳をしのび報恩修行が行なわれます。
總持寺
◇神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-1
◇JR京浜東北線「鶴見駅」徒歩約5分
◇京浜急行線「京急鶴見駅」徒歩約7分
◇京浜急行線「花月総持寺駅」徒歩約7分
◇公式サイト:https://www.sojiji.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
「平常心是道」は禅語のひとつです。瑩山禅師はこれに応じて「茶に逢うては茶を喫し、飯に逢うては飯を喫す(さにおうては さをきっし、はんにおうては はんをきっす)」と答えたそうです。「喫茶喫飯(きっさきっぱん)」、お茶を飲むときはただひたすらお茶を飲み、ご飯を食べるときはただひたすらご飯を食べる。日々の暮らしのなかで物事をひとつひとつ行なうこと、それを続けることでようやく平常心を得られるのかもしれません。
筆者敬白













