■10月10~12日 神戸市垂水区、海神社「秋祭り」です。■
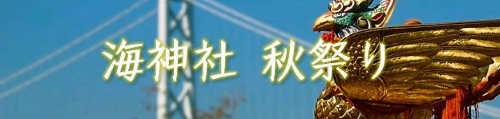
神戸市垂水(たるみ)区、JR垂水駅のすぐそばに鎮座する「海神社(かいじんじゃ)」は、「神功皇后(じんぐうこうごう)」の御代の創建と伝わります。「綿津見神社」との表記もあり。正式には「わたつみじんじゃ」と読みますが、土地の人びとには「かいじんじゃ」と呼ばれることが多いそうです。ほかに「あまじんじゃ」「たるみじんじゃ」とも。式内社(名神大社)で、旧社格は官幣中社。

垂水区は「播磨平野(はりまへいや)」の東の縁で、「六甲山地(ろっこうさんち)」の裾が海岸線近くまでのびる、ゆるやかな丘陵地です。「海神社」の前の国道2号線を渡るとすぐに、兵庫県内でも有数の規模を誇る「垂水漁港」があり、目の前は「明石海峡(あかしかいきょう)」です。海神社本社前と国道2号線沿いに、それぞれ大きな鳥居があります。埋め立てて整備される前は、海側の「大鳥居」のあしもとに砂浜が広がっていたそうです。
土地の歴史は非常に古く、「海神社」から西に700mほどのごく近い場所にある、全長194mの巨大な前方後円墳「五色塚古墳(ごしきづかこふん)」は、4世紀後半に築かれたと考えられています。天平年間には「行基(ぎょうき)」により播磨・摂津の5つの港が開かれ、神戸市域の沿岸は古代の「瀬戸内航路」の重要な拠点として繁栄しました。

社伝によると、「海神社」の由緒は、いまから1800年ほど前にさかのぼります。「神功皇后」が「三韓征伐(さんかんせいばつ)」のあと都へ戻る途中、暴風雨により立ち往生し、皇后自ら「綿津見の三神」をまつり、祈願したところ、たちまち風雨はおさまり、無事に戻ることができました。皇后が綿津見三神をおまつりしたところに社を建てて御神徳を仰いだのが鎮座の由来だと伝わります。

「海神社」の御祭神は、「海神(わたつみ、わだつみ:綿津見、かいじん)三座」として
「上津綿津見神(うわつわたつみのかみ)」海上=航海の神
「中津綿津見神(なかつわたつみのかみ)」海中=魚(漁業)の神
「底津綿津見神(そこつわたつみのかみ)」海底=海藻、塩の神
の3柱を主祭神とし、「大日孁貴尊(おおひるめのむちのみこと)」(天照大神)を配祀しています。水産業や海上輸送で栄えた土地の、海上安全・生業繁栄の神、文字どおり「海の神社」として人びとの崇敬を集めてきましたが、同時に、海は万物が育まれるところであるので、子孫繁栄の神、また安産の守護神としても仰がれます。
◆海神社の秋祭り、垂水の秋祭り
「海神社」の秋の例祭は毎年10月10~12日に行なわれます。10日「宵宮祭」では例祭の無事の斎行を祈願します。11日「例祭」で、氏子崇敬者の繁栄・海上安全・農業繁栄・水産豊漁を祈願します。12日は、「海上渡御(かいじょうとぎょ)」が行なわれます。本社から出御した御神輿が、垂水漁港そばの海岸の御旅所まで練り歩き、そこから神輿を乗せた20数隻の船が海上をめぐります。

垂水区では、五穀豊穣・子孫繁栄・村内安全を祝う神賑行事を総出で行ないます。各地で受け継がれてきた郷土芸能を奉納。獅子舞が舞い、「布団太鼓(ふとんだいこ)」(大型の飾り神輿)が町を練り歩き、お祭りは最高に活気づきます。
海神社
◇兵庫県神戸市垂水区宮本町5-1
◇JR「垂水駅」、山陽電鉄「山陽垂水駅」徒歩1分
◇公式サイト:https://kaijinjya.main.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

「布団太鼓(ふとんだいこ)」とは、大阪河内・泉州地方や兵庫播磨・淡路周辺で担がれる太鼓台のこと。荘厳できらびやかな布団太鼓が力強く練り歩きます。
筆者敬白













