■10月9~11日 久留米、高良大社例大祭「高良山(こうらさん)くんち」です。■
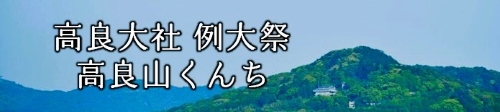
筑後国一之宮「高良大社(こうらたいしゃ)」は、「筑後川(ちくごがわ)」と並行するように東西に約30kmにわたって連なる「耳納連山(みのうれんざん)」の西の端、標高312mの「高良山(こうらさん)」の中腹に鎮座します。旧国幣大社。「九州総社」とも呼ばれます。社伝によると、履中天皇元年(400)社殿が創建され「高良玉垂命(こうらたまたれのみこと)」を祀ったとされます。古くは「高良玉垂宮(こうらたまたれのみや)」と呼ばれました。

御祭神は、正殿に「高良玉垂命」、左殿に「八幡大神(はちまんおおかみ)」、右殿に「住吉大神(すみよしおおかみ)」の3柱です。歴代皇室のご尊崇篤く、久留米藩主からも崇敬を集め、「芸能の神」「武運長久の神」「延命長寿・厄除けの神」として信仰され親しまれています。
「高良玉垂命」が出現したのは、社殿によると陰暦9月13日、いわゆる「十三夜(じゅうさんや)」であり、さらに「月の光とともに出現」したとのことで、月の神さま「月神」としても信仰されています。
現在の社殿は、万治3年(1660)久留米藩第3代藩主、有馬頼利(ありまよりとし)の寄進によるもので、神社建築としては九州最大を誇ります。桃山風の重厚な構えの社殿、山麓の「石造大鳥居」は国の重要文化財に指定されています。「三の鳥居」からのぼる「本坂(ほんざか)」の石段は131段あり、境内の展望所からは久留米の町並みが一望できます。階段横にスロープカーが設置。

本社から山道を20分ほど進むと「奥宮(奥の院)」があり、そこに湧く水は「高良山勝水(かちみず)」と呼ばれ、飲むと勝負に勝つと伝わります。奥宮境内の「水分神社(みくまりじんじゃ)」は、明治の「神仏分離(しんぶつぶんり)」により、かつての神宮寺「高隆寺」の「毘沙門堂」が改められたもの。現在も、「毘沙門天」の縁日である「寅の日」には多くの参拝客が訪れます。

「高良山」は、「筑紫平野(つくしへいや)」と「筑後川」を一望のもとに見渡す位置にあり、宗教的な面ではもちろんのこと、政治・軍事・経済・文化的な要衝として歴史に登場してきました。
麓にある古墳時代前期の方墳「祇園山古墳(ぎおんやまこふん)」をはじめ、多くの遺跡が散在し、古代より「山岳信仰」「山岳霊場」の場であったと考えられています。一説には、高良大社の神宮寺「高隆寺」創建は天武天皇2年(673)とされ、中世から近世にかけての坊院などの跡が大社周辺の尾根に数多く残っていることからも、高良山は、「高良玉垂命」への信仰の場と仏教の僧たちの信仰・修行の場が、古くから重なり合っていたのではないかと考えるひとも少なくありません。
◆列石遺跡「神籠石(こうごいし)」

高良大社の背後から山裾まで、高良山の3分の1をとり囲むように巨大な切石が並ぶ「列石遺跡」があります。諸説あるものの、少なくとも7世紀中葉以前に築かれたのではないかと考えられています。これが明治時代、学会で「神籠石(こうごいし)」という名前で発表されました。
もともと高良大社では、二の鳥居近くの「馬蹄石」など、神の依り代となる岩石を「神籠石」と呼び、列石遺跡を「八葉石(はちようせき)」と呼んでいましたが、紆余曲折を経て学術用語の「神籠石」が定着しました。
「神籠石」は、佐賀から福岡、そして岡山、愛媛、香川、兵庫など瀬戸内海沿岸にかけて10数ヶ所が知られています。神籠石が「霊域」を示すものなのか、「古代山城(こだいさんじょう)」(古代日本の山城)なのかは、いまだに定説がなく謎に満ちています(現時点では古代山城の説が有力なようです)。いずれにせよ古代の重要な遺跡であるのは間違いなく、「高良山神籠石」も国の史跡に指定されています。
◆例大祭「高良山くんち」◆
高良大社の例大祭は「重陽のお祝い」と「秋の収穫祭」が結びついたお祭りで、別名「高良山くんち」。江戸時代には、久留米藩主の代参があり、農具市も立って、筑紫平野の人びとにとって秋一番の楽しみでした。現在、9日「例大祭」、10日「崇敬会大祭」、11日「観月祭」まで例年3日間行なわれます。

お祭りの期間中、小笠原流弓馬術礼法による歩射の神事「百々手式(ももてしき)」や献茶式、野点、獅子舞、「観月祭」では箏曲、琵琶、吟詠、舞囃子、太鼓など、さまざまな「神賑行事(しんしんぎょうじ)」が盛大に行なわれます。

おくんちの日の名物料理は、旬の魚を使った「かます寿司」です。すし飯を背開きしたカマスに詰める姿寿司で、筑後地域の郷土料理です。「カマス」は、スズキ目カマス科カマス属の海水魚で、体長は20~50cmほど。身はやわらかく、ウロコがとれやすいのが特徴です。藁のむしろでつくった米袋を「叺(かます)」といい、魚の「カマス」をかけて、秋の収穫に感謝し五穀豊穣を願うという意味があります。
高良大社
◇福岡県久留米市御井町1番地
◇JR久大線「久留米大学前駅」タクシー15分
◇西鉄「西鉄久留米駅」タクシー30分
◇九州自動車道「久留米IC」から約15分
◇公式サイト:http://www.kourataisya.or.jp













