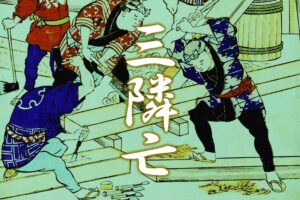■9月20日「彼岸入り」です。■

「彼岸(ひがん)」は暦上の雑節のひとつです。春の「彼岸」は二十四節気の「春分」を挟んだ前後3日ずつの計7日間、秋の彼岸は「秋分」を挟んだ前後3日ずつの計7日間のことをいいます。単に「彼岸」というと春の彼岸をさすので、秋の彼岸を「秋彼岸(あきひがん)」「後の彼岸(のちのひがん)」ということもあります。

「彼岸」の初日を「彼岸入り」、中日(=春分、秋分)を「彼岸の中日(ちゅうにち)」、終わりの日を「彼岸明け」といいます。また、彼岸の期間に営まれる法会を「彼岸会(ひがんえ)」といいます。
彼岸の頃になると、寒暑ようやく峠を越して、しのぎやすくなってくることから、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉が使われるようになりました。
「彼岸」とは「彼の岸(かのきし)」、すなわち「仏の世界」を喩える表現です。悟りの世界であり、涅槃(ねはん:理想)の世界、つまり「極楽浄土(ごくらくじょうど)」のことをいいます。「彼岸」という言葉は、仏典の「波羅蜜多(はらみつた)」という梵語の漢訳「到彼岸(とうひがん)」に由来します。「到彼岸」は、現実の「生死の世界」から煩悩を解脱し、生死を超越した涅槃の世界へ至るという意味です。「彼岸」に対して、煩悩や迷いに満ちたこの世を「此岸(しがん)」といいます
◆西方浄土と彼岸の中日(春分・秋分)

「彼岸の中日=春分・秋分の日」は、昼と夜の長さが等しく、太陽が真西に沈むことから、仏教の「西方浄土(さいほうじょうど)」と関係づけられたといわれています。
「彼岸」の歳時習俗のはじまりは、延暦25年(806)「早良親王(さわらしんのう)」の怨霊を鎮めるための行事だったとする説があります。やがて、法要を営み祖先を祀る行事へとかたちをを変えていきました。お彼岸に先祖の霊を供養し墓参を行なうのは日本独特の風習です。
病のため出家した「藤原道長(ふじわらのみちなが)」は、9体の「阿弥陀如来像」を安置した京都の「無量寿院(むりょうじゅいん)」にて、仏像の手から延びる五色の糸を握り締め、「西方浄土」での極楽往生を信じつつ臨終しました。この姿から仏教信仰と方位観との具体的な結合がみてとれます。

のちに、道長の子「藤原頼道(ふじわらのよりみち)」が天喜元年(1053)に建立した宇治「平等院(びょうどういん)」の「鳳凰堂(ほうおうどう、阿弥陀堂)」には、阿弥陀如来像が安置されています。
平等院の庭と建物は、「浄土庭園」と呼ばれる様式で、「極楽浄土」を表しています。「極楽いぶかしくば宇治の御寺をうやまへ」(極楽が疑わしければ宇治のお寺に参りなさい)といわれました。鳳凰堂の前を流れる「宇治川(うじがわ)」は、「彼岸」と「此岸」を分ける「彼岸の河」に見立てられ、「来世(彼岸)西方浄土(鳳凰堂)」と「現世(此岸)宇治川の対岸」という仮想の世界を現出し、彼岸の中日には鳳凰堂の中央背後(西方)に日が沈みます。
◆四方・八方・十方世界
仏教では、「四方(しほう)=東西南北」と、「四維(しい)=南東・南西・北西・北東」の八方位に、「上・下」を加えた「十方世界(じっぽうせかい)」を説き、そこに諸仏の浄土を描く「十方浄土(じっぽうじょうど)」を観念します。「浄土」は、仏の住む清浄な国土「仏国土(ぶっこくど)」のことで、成仏するために精進する「菩薩(ぼさつ)」の世界です。泥中に染まらず、そこから華をひらく「蓮(はす)」に喩えられる「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」です。
「東方浄土」薬師如来(やくしにょらい)の「浄瑠璃世界(じょうるりせかい)」
「西方浄土」阿弥陀如来(あみだにょらい)の「極楽浄土」
「南方浄土」観音菩薩(かんのんぼさつ)の「補陀落(ふだらく)」
「北方浄土」弥靭菩薩(みろくぼさつ)の「兜率天(とそつてん)」

◆ほたもち・おはぎ
お彼岸の供物として作られる、蒸した米を軽くついてまとめ、餡(あん)をまぶした餅のことを、春は「牡丹」の花が咲くことにちなんで「牡丹餅(ぼたもち)」、秋は「萩」の花が咲くので「御萩(おはぎ)」と呼びます。夏には「夜船(よふね)」、冬には「北窓(きたまど)」など呼び名もさまざまで、お彼岸にかぎらず一年中、日本全国で好まれる和菓子です。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
お彼岸を機会に先祖の墓参に出向きましょう。無心の愛で育ててくれた両親・祖父母なら、この局面をどう判断するだろうか、など日頃声に出せないことを墓前で問いかけてみましょう。亡き先祖の声がきっと心に届くことでしょう。
読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白