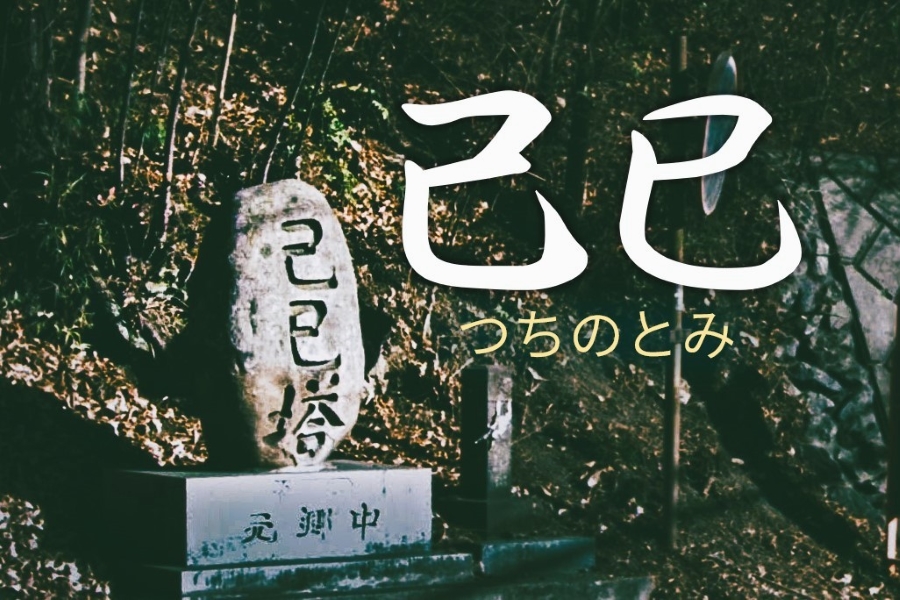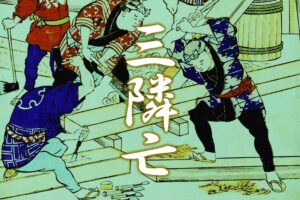■8月28日「己巳(つちのとみ)」です。■

「己巳(つちのとみ、きし)」は、「干支(十干と十二支)」〔※〕の組み合わせ60のうちの6番目で、「弁才天(べんざいてん)」を祭る日とされています。「巳待(みまち)」ともいいます。

「五行説(ごぎょうせつ)」〔※〕で、十干「己(つちのと、き)」は「陰の土」、十二支「巳(み、し)」は「陰の火」で、「相生(そうじょう)」〔※〕では「火生土」となり相性のいい日です。「庚申(こうしん)」や「甲子(きのえね)」と同様に中国から渡ってきた行事ですが、「己巳」や「七福神」は日本独自のものです。
「巳」には「蛇」をあてています。蛇は弁才天の使いであると考えられていたことから、福徳賦与の神である弁才天を祀るようになりました。
弁才天は、宝冠を被り青衣をまとった美しい女神で、左手に弓、刀、斧、絹索(けんじゃく、けんさく:仏が人を救いあげる慈悲の投げ縄)を、右手に箭(や:矢)、三鈷戟(さんこしょ)、独鈷杵(とっこしょ)、鉄輪を持つものもあり、ヴィーナ(琵琶に似た楽器)を奏する音楽の神のかたちをとっています。
弁才天は全国の弁天社や弁天堂に数多く祀られていますが、
安芸宮島「大願寺(だいがんじ)」
大和天川「天河大辨財天社(てんかわだいべんざいてんしゃ)」
近江の竹生島(ちくぶしま)「都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ、竹生島神社)」
相模の江ノ島「江島神社(えのしまじんじゃ)」
陸前の金華山(きんかざん)「黄金山神社(こがねやまじんじゃ)」
は「五弁天(ごべんてん)」と呼ばれ、特に知られています。そのほか、鎌倉の「銭洗弁財天(ぜにあらいべんざいてん)」(宇賀福神社)は、境内奥の洞窟内の湧き水で銭を洗うと数倍になって返ってくるとされ、ご利益にあずかろうと多くのひとが訪れます。

日本各地の海や湖沼の浦、浜、磯にある「弁天島(べんてんじま)」と呼ばれる島は、弁才天信仰に由来します。なかには、人工の島や陸繋島(りくけいとう:砂州で陸続きになった島)もあります。海難除けや豊漁祈願の守り神として、昔から土地の人びとに祀られてきました。
※十二支(じゅうにし)
子(ネズミ)・丑(牛)・寅(トラ)・卯(うさぎ)・竜(龍)・未(蛇)・午(馬)・羊(ヒツジ)・申(サル)・酉(にわとり)・戌(犬)・猪(いのしし)の12種の動物を表わす漢字のこと。「十干(じっかん)」※と組み合わせることで、60を1周期とする「干支(えと)」を形成し、方角や時間、暦に用いられる。また、陰陽五行説と組み合わせることで「卦(け)」にも応用されるようになった。
※十干(じっかん)
木・火・土・金(ごん)・水の五行(五行)を兄(え)・弟(と)に分けたもの。年・日を現す。甲(きのえ)・乙(きのと)・丙(ひのえ)・丁(ひのと)・戊(つちのえ)・己(つちのと)・庚(かのえ)・辛(かのと)・壬(みずのえ)・癸(みずのと)を十二支と組み合わせて使う。
※五行(ごぎょう)、五行思想(ごぎょうしそう)、五行説(ごぎょうせつ)
古代中国に端を発する自然哲学の思想。万物は火・水・木・金・土の5種類の元素からなるという説である。その根底には、5種類の元素は「互いに影響を与え合い、その生滅盛衰によって天地万物が変化し、循環する」という考え方がある。西洋の四大元素説(四元素説)と比較される東洋思想。
※五行相生(ごぎょうそうじょう)
五行説で、五行に相生(一緒に、または、並んで生育すること)の関係があり、順序立てるとした説。木から火が、火から土が、土から金が、金から水が、水から木が生じるというように、五行は、木火土金水の順に循環するという考え。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

現代社会では、経験的な習慣の「己巳」や「庚申」などが、単なる迷信と同じ扱いを受けます。暦の謂れを振り返ってみることも、世知辛い時代における心の余裕といえます。
皆様、時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白