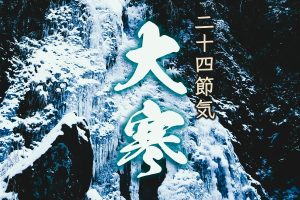◆二十四節気◆令和7年(2025)8月23日「処暑(しょしょ)」です。◆
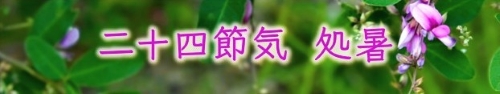
8月23日5時34分「処暑」です。旧暦7月、申(さる)の月の中気で、新暦8月23日頃。天文学的には、太陽が黄経150度の点を通過するときをいいます。

「処」(旧字体「處」)は、「その場所にいる、とどまる、落ち着く」などを意味し、「処暑」は、暑さが落ち着いて、ひと段落することを表しています。『暦便覧』では、「陽気とどまりて、初めて退きやまんとすれば也」と説いています。
涼風が吹きわたる初秋の頃です。暑さは峠を越えて、ようやく過ごしやすくなります。「綿(わた)の花」が開きます。穀物が実り始め、収穫も目前といった時期です。マツムシやコオロギといった秋の「虫の声」もそろそろ聞こえてきます。
また、この時期は「八朔」「二百十日」「二百二十日」と並び台風襲来の時期とされています。暴風雨に見舞われることも少なくありません。
日に日に北から秋の気配がしてきます。道端や河川敷では風に揺れる「ススキ」の姿を見かけるようになります。残暑厳しいなかでも秋の気を感じます。台風でさえも秋の気は感じられるものです。
処暑なりと熱き番茶を貰ひけり――草間時彦
(まだ残暑がつづくが、今日は処暑であるので、熱い番茶を所望した)
秋は、感じかた次第で長くもあり、また、あっというまに過ぎてしまうようでもあります。人間の感性にゆだねられる秋という季節には自然と「もの悲しさ」が含まれるように思われます。

◆◆七十二侯◆◆
◆初候「綿柎開」(めんぷひらく)
◇綿を包む萼(がく)が開く。
◇「柎(あし、いかだ、うてな)」:鐘や鼓をかける台の脚。花の萼。いかだ(桴、泭)。
◆次候「天地始粛」(てんちはじめてさむし)
◇ようやく暑さが鎮まる。
◆末候「禾乃登」(こくものすなわちみのる)
◇穀物が実る時節。
◇「禾(いね、のぎ)」:稲、穀物。芒(のぎ:イネ科植物でもみがらと呼んでいる部分の先端から出ている針状の突起)
◆◆8月 処暑の頃の花◆◆

「綿(わた)」 cotton plant アオイ科ワタ属の総称 学名 Gossypium
ワタ属は、繊維作物として世界各地で栽培されている多年生草本植物です。種子表面の毛(繊維細胞)を利用します。年平均気温15℃以上の熱帯から温帯の南部に約40種が分布しています。
花の開花時期は9月頃。開花後5週間くらいすると実が熟して、はじけて綿毛に包まれた種子、いわゆる「綿花(めんか」が外に吹き出します。綿毛は種子の表面の細胞が伸びたもの。
綿毛は綿糸・綿織物の原料、ふとん綿、脱脂綿、さまざまな充填料などに使われます。種子からは品質の良い油が採れ、てんぷら油、サラダ油、マヨネーズなどに用いられます。

ワタは、古代から人間に利用されてきました。ワタの果実や綿糸が、紀元前5800年頃のものがメキシコの遺跡から、紀元前2400年頃のものがワカ・プリエタ遺跡(ペルー)から、紀元前3500年頃のものがモヘンジョダロ遺跡(インド)から発掘されています。
日本に伝来したのは、桓武天皇の時代、延暦18年(799)三河国に漂着した天竺人(インド人)が種子を持ち込んだのが初めといわれています。栽培が広まったのは、中国から種子が導入された文禄年間(1592~1595)だとされています。以来、ワタを「木綿(もめん)」と呼び、蚕の繭から作られるものを「真綿(まわた)」と呼ぶようになりました。
愛知県西尾市に鎮座する「天竹神社(てんじくじんじゃ)」は、日本に初めて綿の種子を伝えたとされる崑崙人(こんろんじん:中国から見たインド人)を、綿の神「新波陀神(にいはたがみ)」として祀ります。日本でも珍しい「綿」にまつわる神社です。毎年10月に行なわれる祭礼「棉祖祭(めんそさい)」では、「舟みこし」が担がれ、古式ゆかしい「綿打ち」の儀式が執り行なわれます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

8月後半になると、朝晩の涼しさを感じます。7月後半から8月は夏の花火大会のピークでした。花火大会に出かける浴衣姿も、処暑の頃になるとすこし減ったように感じます。
処暑を過ぎると、これからは台風到来の季節です。
残暑の疲れが出て、食欲不振や精力減退の方に、お勧めは規則正しい生活です。
皆さん、お体ご自愛専一の程
筆者敬白