■8月19~20日 秋田県鹿角市「花輪ばやし」です。■
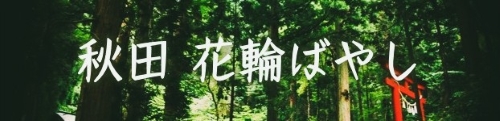
「花輪ばやし(はなわばやし)」は、秋田県「鹿角市(かづのし)」のお祭りで、鹿角市の代表的な民俗芸能です。毎年8月19~20日に行なわれます。国の重要無形民俗文化財に指定、さらに、ユネスコ無形文化遺産に登録されています。「日本三大ばやし」のひとつ。

「花輪ばやし」は、花輪の総鎮守「幸稲荷神社(さきわいいなりじんじゃ)」に奉納される祭ばやしです。幸稲荷神社は、建仁4(元久元)年(1204)伊勢両宮の分霊の際に御神霊を分け、祭祀創設されたと伝わります。御祭神は「豊受姫命(とようけひめのみこと)」「猿田彦命(さるたひこのみこと)」「天宇都女命(あめのうずめのみこと)」。本殿は、岩手県八幡平市との境にある標高1,122mの「皮投嶽(かわなげだけ)」の山麓に位置し、土地の人びとに「産土神さん(うぶすなさん)」呼ばれて親しまれ、古くから厚い信仰を受けています。
「花輪ばやし」の起源は、平安末期、都から流れてきた貴人の笛の曲に、後世、太鼓・鉦・三味線がついて、現在のような形になったと考えられています。「花輪ばやし」のお囃子は伝承の過程で、各町内ごとに特徴が出るようになりました。また、古くから伝わる曲に加えて、独自の新曲を演奏する町内もあらわれました。このようにして、江戸中期以降、新しい曲が追加されていったと考えられ、現在は12曲が伝承されています。

「花輪ばやし」のお祭りに使われる「屋台(やたい)」(山車)の底には床がなく、お囃子の演奏者が歩く形式の「腰抜け屋台」と呼ばれるものです。全10町内の屋台は、各町内自慢の金箔、総漆塗りなどが施されている豪華絢爛なもの。古いもので明治12年(1879)に作られた屋台もあります。

祭典は、お盆明けの8月19日夕方、のろしを合図に「御旅所」に向かってパレードを開始します。幸稲荷神社に開始の挨拶。「サンサ」を行ないます。「サンサ」とは、全町で円陣を組んで行なわれる手締め式のこと。「サンサンサントセ、オササノサントセ、ヨイヨイヨーイ」と、3度繰り返し唱えます。「サンサ」は、祭りの行事のなかの要所要所で行なわれます。
パレードは御旅所から駅前広場へ。「花輪ばやし」最大の見どころです。全町内揃い踏み円陣を組んでお囃子の競演などが行なわれます。
20日未明の「朝詰(あさづめ)」では、華麗な屋台が若者たちの手によって町内をねり歩き、「枡形(ますがた)」と呼ばれる神輿の控え所に詰める様は、まさに豪華絢爛。「枡形」は、旧城下町にみられる街のつくりで、敵が一気に攻められないよう街並みがカギの形状になっていることをさします。

途中、他町内を通過する際、町内の代表による「町境の挨拶(ちょうざかいのあいさつ)」が行なわれます。
「○○町内申し上げます。かねてお約束の時間に参上いたしました。ただ今から××町内をお通し願います」
「××町内申し上げます。ただ今の○○町内のお申し出確かに承知いたしました。どうぞお通り下さい」
このようなやり取りが交わされます。ただし、これはスムーズにいった場合で、たびたび挨拶がこじれて、けんか屋台に発展するといった荒っぽい一面も見られるそうです。
「枡形」で行なわれる奉納演奏では、それまでの威勢のいいお囃子とは違い、荘厳な雰囲気の伝承曲が奏でられます。躍動的なパレードと趣向が変わり、一転、厳粛な神事となります。
花輪ばやし
◇JR花輪線「鹿角花輪駅」駅前ほか
◇公式サイト(花輪ばやし祭典委員会事務局):https://www.hanawabayashi.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
「日本三大ばやし」には諸説あります。ここではどれが正しいかではなく、皆を紹介しておきます。
・祇園囃子(京都府、祇園祭)
・葛西囃子(東京都、葛西神社)
・神田囃子(東京都、神田神社)
・花輪囃子(秋田県、鹿角市)
・佐原囃子(千葉県、佐原市)
それぞれが「日本三大ばやし」のひとつだと主張していますが、唯一「祇園ばやし」のみ常に3つのなかに数えられているようです。いずれにせよ、どの囃子も歴史を持ち伝統を受け継いでいます。
まだまだ暑い日が続きますが、日が沈んだ頃に吹く風は気持ちよくなってきました。東北の夕涼みに是非お出かけ下さい。
筆者敬白













