■8月19~21日「鎌倉宮(かまくらぐう)例祭」です。■
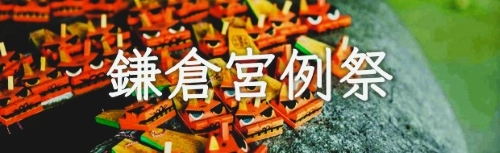
「鎌倉宮(かまくらぐう)」は、神奈川県鎌倉市二階堂にある神社で、「建武中興十五社(けんむちゅうこうじゅうごしゃ)」の一社、「護良親王(もりながしんのう、もりよししんのう)」を祀ります。旧社格は官幣中社。神社本庁の包括下には入らない「単立神社」です。
「建武中興十五社」とは、「建武の中興(建武の新政)」に尽力した南朝側の皇族・武将などを主祭神とする15の神社のことです。「後醍醐天皇(ごだいごてんのう)」による「建武の中興」は、それまでの武家中心の社会から天皇中心の社会に戻そうとしたものでした。これは、「明治維新」によって江戸幕府から実権を取り戻して明治政府を樹立した「明治天皇(めいじてんのう)」にとって意義深いものでした。そして、明治以降、建武の中興に関わった人びとを祀る神社がその縁地などに作られたのです。
◎建武中興十五社[社名(所在地)ー創建ー主祭神]
吉野神宮(奈良県吉野郡吉野町)明治25年(1892)ー後醍醐天皇
鎌倉宮(神奈川県鎌倉市)明治2年(1869)ー護良親王
井伊谷宮(静岡県浜松市浜名区)明治5年(1872)ー宗良親王
八代宮(熊本県八代市)明治17年(1884)ー懐良親王
金崎宮(福井県敦賀市)明治23年(1890)ー尊良親王、恒良親王
小御門神社(千葉県成田市)明治15年(1882)―花山院師賢
菊池神社(熊本県菊池市)明治3年(1870)ー菊池武時、菊池武重、菊池武光
湊川神社(神戸市中央区)明治5年(1872)ー楠木正成
名和神社(鳥取県西伯郡大山町名和)承応・明暦の頃(1652~57)ー名和長年
阿部野神社(大阪市阿倍野区北畠)明治15年(1882)ー北畠親房、北畠顕家
藤島神社(福井県福井市)明治3年(1870)ー新田義貞
結城神社(三重県津市)文政7年(1824)ー結城宗広
霊山神社(福島県伊達市)明治14年(1881)ー北畠親房、北畠顕家、北畠顕信、北畠守親
四條畷神社(大阪府四條畷市)明治23年(1890)ー楠木正行
北畠神社(三重県津市)寛永20年(1643)ー北畠顕能、北畠親房、北畠顕家
「護良親王」は、延慶元年(1308)「後醍醐天皇(ごだいごてんのう)」の皇子として誕生。6歳のとき僧籍に入って「尊雲法親王(そんうんほっしんのう)」と号し、京都の「梶井門跡(かじいもんぜき:三千院)」に入りました。

11歳で「比叡山延暦寺(ひえいざんえんりゃくじ)」に入室。理髪聡明、非凡な才能の持ち主で、弱冠20歳にして「天台座主(てんだいざす)」となりました。その後、「梶井門跡(かじいもんぜき)」を継承、「門主(もんしゅ)」となります。
当時の「天台座主」は、政治経済的・軍事的に強い力を持っていました。折しも鎌倉幕府を倒して天皇中心の政治を取り戻そうと計画していた後醍醐天皇が、皇子を天台座主に据えたのだろうといわれています。
政権回復をめざす「後醍醐天皇」は、鎌倉幕府打倒に2度失敗し、隠岐(おき)に流されましたが脱出。幕府に不満を持っていた武士たちを味方につけ、元弘3年(1333)幕府を倒し、その翌年の建武元年(1334)「建武の中興(建武の新政)」を開始しました。八面六臂の活躍を見せ、鎌倉幕府倒幕に多大な貢献をした「護良親王」は「征夷大将軍」に任命されました。

しかし、建武政権は安定を欠き、再び政権に不満を抱いた武士たちに「足利尊氏(あしかがたかうじ)」が呼びかけ、武家政治の再興をはかって兵を挙げました。そして、足利方が勝利し、建武政権は崩壊、「室町幕府」が成立しました。
「護良親王」は、建武元年(1334)、足利尊氏との対立し鎌倉二階堂の「東光寺(とうこうじ)」に幽閉されてしまいます。そして、建武2年(1335)「中先代の乱(なかせんだいのらん)」の混乱のなか、尊氏の弟「足利直義(あしかがただよし)」の命を受けた「淵辺義博(ふちべよしひろ)」によって暗殺されました。御年わずか28歳でした。

明治2年(1869)2月、「明治天皇」は建武中興に尽力した護良親王の功を賛え、親王を祀る神社の造営を命じました。6月に「鎌倉宮」の社号が下賜され、7月、現在の地(東光寺跡)に社殿が造営されました。
「護良親王」は、幕府の追手から逃れながら、各地で潜伏していた際、大和国「吉野(よしの)」にある「十津川村(とつかわむら)」で還俗し、このときから「護良親王」と名乗りました。また、比叡山延暦寺にいたころ「大塔」という場所に居を構えたことから(諸説あり)、通称「大塔宮」とも呼ばれます。
「大塔宮 護良親王」を、歴史的には「おおとうのみや もりよししんのう」と読んだと考えられていますが、鎌倉宮の主祭神としては「もりながしんのう」といい、そして土地の人びとは鎌倉宮を「だいとうのみや」「だいとのみや」と呼ぶことが多いそうです。
◆例祭
鎌倉宮の例祭は、護良親王の薨去の日をもとに、8月19日から21日まで、3日間にわたり行なわれます。
19日「前夜祭」「子ども神輿」「奉納演芸大会」「盆踊り」
20日「例祭」「盆踊り」
21日「後鎮祭(こうちんさい、のちしずめのみまつり)」
19、20日の夕方からは提灯がともり、夜店も出て、境内に設置された櫓を中心に盆踊りを踊るひと、見物するひとで賑わいます。

鎌倉宮
◇神奈川県鎌倉市二階堂154
◇JR「鎌倉駅」からバス「鎌倉宮行き」終点下車すぐ、「大塔宮行き」で「大塔宮」下車徒歩1分
◇公式サイト:https://www.kamakuraguu.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
いつの時代も、権力欲による争いはなくならないものです。どのような状況下でも正しく判断し、信念から心願を成就する、いわゆる大願成就が苦境を超える心の支柱でしょう。
季節の変わり目です。皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白













