■8月1日 諏訪大社「お舟祭」です。■
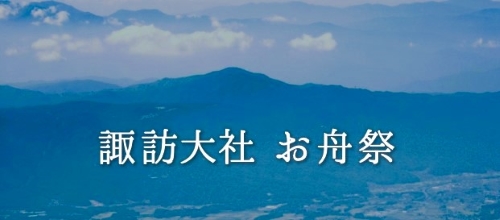
「諏訪大社(すわたいしゃ)」は、長野県の「諏訪湖(すわこ)」を挟むように鎮座する2社4宮からなる神社です。信濃国一之宮。信濃国四十八座の第一。神階は正一位。式内社(名神大社)。全国に約25,000社ある「諏訪神社(すわじんじゃ)」の総本社です。平安中期に編纂された『延喜式神名帳』には「南方刀美神社(みなかたとみのかみのやしろ)」と記されています。

起源については諸説ありますが、『古事記』の「国譲り(くにゆずり)」神話にまでさかのぼり、少なくとも1500年から2000年前の創建と推定される、日本で最も古い神社のひとつに数えられます。旧称は「諏訪神社」。「お諏訪さま」「諏訪大明神」などと呼ばれて親しまれ、寅年と酉年に行なわれる「御柱祭(おんばしらさい)」は全国的に有名です。
御祭神は、主祭神「建御名方神(たけみなかたのかみ)」「八坂刀売神(やさかとめのかみ)」と、配祀神「八重事代主神 (やえことしろぬしのかみ)」です。

諏訪湖の南岸に「上社(かみしゃ)」、北岸に「下社(しもしゃ)」があり、上社が下社に対して上流の位置にあります。さらに、上社は「前宮(まえみや)」と「本宮(ほんみや)」、下社は「春宮(はるみや)」と「秋宮(あきみや)」が鎮座します。氏子地域は、諏訪地方全体に広がります。
上社
・前宮――八坂刀売神
・本宮――建御名方神
下社
・春宮・秋宮――建御名方神、八坂刀売神、八重事代主神
境内建物は、社殿の四隅に「御柱(おんばしら)」と呼ばれるモミの大木が建ち、本殿を持たず、拝殿のうしろに幣殿(へいでん)、左右片拝殿(さゆうかたはいでん)が続く独自の配置で「諏訪造(すわづくり)」と呼ばれます。本殿を持たず、自然そのものを御神体とする古来からの信仰の姿を現在に伝えています。

「建御名方神」は、雨や風を司り、信濃国を開拓したことから、農業・狩猟・航海・勝負の守り神として信仰されてきました。殺生が禁じられていた時代にも、諏訪の人びとは「お諏訪さま」から狩をすることを許され、鹿肉を食べていました。また、武家の守護神として、歴代の将軍をはじめ多くの武将たちより篤い信仰を受けてきました。

◆お舟祭(おふねまつり)
「お舟祭(おふねまつり)」は、下社の例大祭で、「御霊代(みたましろ:御神体)」を春宮から秋宮に移す「遷座祭(せんざさい)」です。下社では、2月1日に御霊代を秋宮から春宮に、8月1日に春宮から秋宮に遷座しますが、特に夏の遷座祭「お舟祭」は多くの人が集まり賑わいます。

御霊代を運ぶ神幸行列に続いて、「翁(おきな)と媼(おうな)の人形」を乗せた「柴舟(しばぶね)」を曳行することから「お舟祭」と呼ばれるようになったといわれます。翁と媼の人形は、保存会の人びとが作り、氏子たちは「爺婆(じじばば)」と呼んでいるそうです。柴船は、角柱6本を組み合わせ、刈ってきた青柴(葉をつけた雑木)を舟に見立てて飾り付けます。
柴舟の曳行は、10年に1回まわってくる輪番の「御頭郷(おとうごう、おんとうごう)」が担当します。「頭」は「頭番=当番」を意味し、「郷」は諏訪をいくつかに分けた地区のことです。長さ12メートル、重さ5トンという巨大な「お舟」を数百人の「御頭郷」が力いっぱい曳行します。
諏訪大社
上社本宮 長野県諏訪市中洲宮山1
上社前宮 長野県茅野市宮川2030
下社春宮 長野県諏訪郡下諏訪町193
下社秋宮 長野県諏訪郡下諏訪町5828
◇公式サイト:https://suwataisha.or.jp
◆お舟祭りの催し物及び交通規制について(下諏訪町):https://www.town.shimosuwa.lg.jp/www/contents/1499778217737/index.html
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

諏訪大社には本殿と呼ばれる建物がありません。代わりに「秋宮」はイチイ(一位)の木を、「春宮」は杉の木を御神木とし、「上社」は御山を御神体として拝しています。諏訪大社は、社殿をもたなかったといわれる古代の神社の姿を今に残しています。
暑いさなかの祭礼です。水分を十分に補給してお出かけください。
皆さま、お体ご自愛専一の程
筆者敬白













