■7月7日 奈良吉野、金峯山寺「蛙飛び」です。■
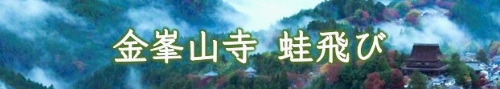
大和国の「吉野山(よしのやま)」から「大峰山(大峯山、おおみねさん)」山上ヶ岳(さんじょうがたけ)にかけての一帯は、古くは「金の御岳(かねのみたけ)」「金峯山(きんぷせん)」と称する「修験道(しゅげんどう)」の聖域でした。古代から「山岳信仰」の聖地であり、平安時代以降は「霊場」として信仰を集めてきました。

「吉野・大峯」の霊場は、「高野山(こうやさん)」と「熊野三山」およびこれら霊場同士を結ぶ巡礼路とともに「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されています。
吉野山にある「金峯山寺(きんぷせんじ)」は、「金峯山修験本宗(きんぷせんしゅげんほんしゅう)」の総本山です。山号は「国軸山(こくじくさん)」。

白鳳時代に修験道の開祖「役小角(えんのおづぬ)」が、「山上ヶ岳」で1000日間の参籠修行を成し遂げ、「金剛蔵王大権現(こんごうざおうだいごんげん)」を感得し、修験道の本尊としました。その姿を山桜(やまざくら)の木に刻んで、「山上ヶ岳」の頂上と山下(さんげ)にあたる「吉野山」に祀ったのが、「金峯山寺」の開創と伝わります。
「蔵王堂(ざおうどう)」(国宝)に安置されている3躯の「蔵王権現(ざおうごんげん)」は、7mの高さの巨大な立像(りゅうぞう)で、仏教の仏とも神道の神ともつかない独特の尊格(そんかく)です。青黒い体に、忿怒(ふんぬ)の相。普段は厨子の戸帳の奥に祀られている「秘仏(ひぶつ)」です。
◆蓮華会(れんげえ)と蛙飛び行事

「蓮華会(れんげえ)」は、金峯山寺の三大行事のひとつで、役行者が産湯をつかったと伝わる大和高田市奥田にある「捨篠池(すてしのいけ)」で刈り取った清浄な「蓮の花」を蔵王権現に供える法会です。ロープウェー「吉野山駅」で、蓮を運ぶ一行と「大青蛙」を乗せた太鼓台が合流し、太鼓と独特のかけ声で金峯山寺蔵王堂までをにぎやかに練り歩きます。
大青蛙を乗せた太鼓台が蔵王堂へ練り込み、法要ののち、「蛙飛び」の儀式が行なわれます。最後に、導師の授戒によってめでたく人間の姿に戻ります。
仏罰を受けた男が蛙の姿に変えられ、改心して人間の姿に戻るまでを再現しています。

延久年間(1069頃)のこと、金峯山へ参詣する修験者の一行のなかに、つねづね金峯山蔵王権現の修験道神力を侮った男がいました。あるとき、この男が行者の精進や仏の力を侮辱する言葉を吐くと、突然、空一面まっ黒な雲につつまれ、男は一羽の大鷲(おおわし)に断崖絶壁に置き去りにされてしまったのです。
男は大声で助けを求めますが、助けが来ません。怖くなり震えていると、そこに高僧が現れて、助けるためには改心しなければと咎めました。男が改心を誓ったので、僧は、絶壁から降りやすいようにと、法力で男を蛙の姿に変え、無事に救われたのです。
僧は蛙の姿の男を蔵王堂につれて帰りました。そして吉野全山の僧が集まり読経し、最後には導師の授戒によって、男は無事に人間の姿に戻りました。
金峯山寺
◇奈良県吉野郡吉野町吉野山2498
◇近鉄「吉野駅」下車、ロープウェイ「山上駅」より徒歩10分
◇公式サイト:https://www.kinpusen.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
金峯山寺で7月7日に行なわれる「蛙飛び」では、大青蛙を乗せた太鼓台が蔵王堂へ練り込み、法要の後、蛙飛びの作法が行なわれます。天気が良ければ観光にはよい季節です。
これから本格的な夏。読者の皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白













