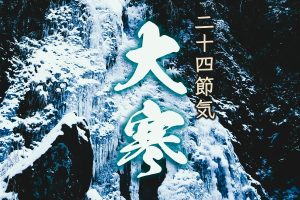◆二十四節気◆令和7年(2025)7月7日「小暑(しょうしょ)」です。◆
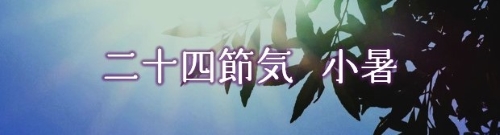
7月7日5時05分「小暑(しょうしょ)」です。旧暦5~6月、未(ひつじ)の月の正節で、新暦7月7日頃。天文学的には、太陽が黄経105度の点を通過するときをいいます。

「梅雨明け」が近づき、暑さが本格的になる頃で、「暦便覧」には「大暑来れる前なればなり」とあります。「夏至(げし)」を境に日足は徐々に短くなりますが、夏の太陽が照り付けて、暑さは日増しに厳しくなってきます。「蓮の花」が咲き始め、「鷹の子」が巣立ちの準備を始め、「蝉」が鳴き始めます。一方、梅雨の終わりごろには「集中豪雨」で被害が出ることも多いため、注意が必要です。
「小暑」の日から「暑気(しょき、あつけ、あつき)」に入ります。「小暑」から「立秋」までのあいだが「暑中(しょちゅう)」で「暑中見舞い」はこの期間に送ります。「暑中」の期間は、「夏の土用」の約18日間(=「立秋」前の18日間)としたり、梅雨明けから「立秋」前までとしたりすることもあります。
◆七夕(たなばた)◆
「小暑」のころの行事、7月7日の「七夕(たなばた)」は、「五節句」のひとつ「七夕(しちせき)」の日です。古く中国から伝来した行事と、日本古来の伝承と盆行事などの要素が入り混じり、現在まで伝わってきました。もともとは陰暦の7月7日に行なわれていました。現在は、新暦7月7日に行なわれ、「短冊(たんざく」に願い事を書き、「笹」や「竹」に飾るのが一般的です。
◆◆「七十二侯」◆◆
◆初候「温風至」(おんぷう いたる)
◇暑い風が吹いて来る時節。
◆次候「蓮始開」(はす はじめて はなさく)
◇蓮の花が開き始める。
◆末候「鷹乃学習」(たか すなわち がくしゅうす
◇鷹の幼鳥が飛ぶことを覚える。

◆◆「7月の花」◆◆
★朝顔(あさがお)
開花時期は7月1日~10月10日頃。原産は中国で、平安時代に日本に渡来しました。朝のうちだけ開花するので「朝顔」と呼ばれますが、日陰に咲くものは夕方まで咲き続けることもあります。
古代中国では高価な薬として牛と取引されたほどです。漢名を「牽牛(けんぎゅう)」とする所以です。漢方では現在でも種子が下剤や利尿剤として使われています。花言葉は「愛情」「平静」「結束」「短い愛」「はかない恋」など。

★半夏生(はんげしょう)
Saururus の語源は、ギリシャ語の「sauros(トカゲ)+oura(尾)」。トカゲの尾のような穂状の花を咲かせます。七十二候の「半夏生」の頃になると、葉がペンキを塗ったかのように白くなることから、名が付いたとも伝わります。「半化粧」「片白草」とも呼ばれます。
開花時期は、7月1日~20日頃。花の時期に葉が白くなるのは虫を誘うためで、夏が終わると葉はもとの緑色に戻ります。山の水辺に群生することが多いですが、都会でも時々植えられてるのを見かけます。

★鬼灯(ほおづき)
花びらは五角形で、開花時期は6~7月。オレンジ色の実の中に、オレンジ色の球体があり、これが本当の実です。
「ほおつき」(頬突き)は、子供が口に入れて鳴らす頬の様子から名前がつきました。「鬼燈」「酸漿」とも書きます。花言葉は「心の平安」「不思議」「自然美」「いつわり」。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
梅雨明け宣言が沖縄・九州から次第に北上してきました。これから本格的な夏がやってきます。感染症への注意もまだまだ緩められないようです。
食事・睡眠をよくとり、体調の維持に努めましょう。皆様、お体ご自愛専一の程
筆者敬白