■6月5日 京都宇治・縣神社(あがたじんじゃ)「あがた祭」です。■
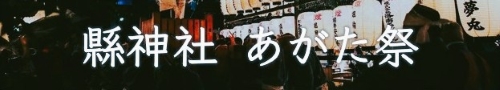
宇治の「平等院(びょうどういん)」のすぐ南西に位置する「縣神社(あがたじんじゃ)」は、神話に名高い「木花開耶姫命(このはなさくやひめのみこと)」を祀ります。「あがたさん」と呼ばれ親しまれてきた千数百年の歴史を有する古社で、良縁・安産の守護神として敬われています。

縣神社は、その名の示すとおり、上古の「縣(あがた)」の守護神であったと考えられています。「縣(県)」とは、古代の氏族制度における行政単位のひとつで、皇室の直轄地であり、特に近畿地方に多く散在していました。縣神社は、「宇治川(うじがわ)」両岸に広がる地域を「宇縣」「宇治縣」と称した時代に、地主神として奉祀されたものと考えられます。
その後、律令制下で「国郡里制(こくぐんりせい)」という地方区分が確立すると「縣」は地域区分の単位としては用いられなくなり、郡名など地名の一部に名残りをとどめるようになりました。
永承7年(1052)の平等院の建立にあたり、縣神社は平等院の総鎮守になったとされ、明治維新まで三井寺円満院(みいでら えんまんいん)の支配下にありました。明治の「神仏分離令」により、三井寺から独立。
正面鳥居を入って左側、醴水舎の北にある井戸は「縣井(あがたい)」といい、平安時代以来、歌枕にしばしば詠まれています。
かはず鳴く縣の井戸に春暮れて散りやしぬらん山吹の花(後鳥羽院『続後撰和歌集』)
都人きても折らなんかはづ鳴くあがたのゐどの山吹のはな(よみ人しらず『続後撰和歌集』)
山吹の花もてはやす人もなし縣の井戸は都ならねば(妙光寺内大臣『新葉和歌集』)
神聖なる井泉は、上古より今日まで連綿と良質な水が湧き出ていて、今でも献茶祭など神社の行事に使われています。
◆あがた祭
毎年6月5日から6日未明にかけて行なわれる「あがた祭」は、昼ごろから通りにびっしり露店が並び、十数万人の人出で賑わう宇治最大のお祭りです。特に5日深夜の「梵天渡御(ぼんてんとぎょ)」は、周りの商店や家の燈火が一切禁ぜられ、暗闇の中で執り行われるため、別名「暗夜の奇祭」としても有名です。

祭りは「朝御饌ノ儀(あさみけのぎ)」で始まり、夕方5時、「夕御饌ノ儀(ゆうみけのぎ)」が斎行されたあと、深夜、梵天渡御が始まります。

「梵天」とは、1600枚もの奉書紙を短冊に切って束ねた御幣を青竹に挟みこんだもの。直径1m程の球形をしています。重さは50kg超。深夜11時、梵天が地元の梵天講の若者たちに担がれ動き出します。境内や沿道の露店、町の明かりが一斉に消されます。本殿において真っ暗闇のなかで「神移し」の秘儀を執行し、出御となります。
境内を練り歩き鳥居をくぐって表に出た梵天は、旧大幣殿前で「ぶん回し」や「差し上げ」など勇壮に走り回ります。神の依代である梵天が通過するあいだは、家々は明かりを落としてそれを迎えます。かつて何をしてもかまわないという「無礼講の夜」として男女が盛り上がる祭りだったこともあるとか。この後、旅所の梵天は再び縣神社に戻り、遷幸祭が行なわれます。
■縣神社■
◇京都府宇治市蓮華72
◇JR奈良線「宇治駅」から徒歩約9分
◇京阪宇治線「宇治駅」から徒歩約10分
◇公式サイト:https://agatajinjya.com













