■6月4~10日「歯と口の健康週間」です。■
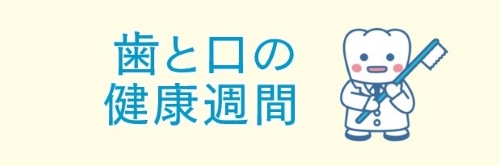
日本歯科医師会(にほんしかいしかい)は、昭和3年(1928)から昭和13年(1938)まで、「6(む)4(し)」にちなんで、6月4日に「虫歯予防デー」を実施していました。その後、「護歯日」、「健民ムシ歯予防運動」となり、昭和18~22年(1943~47)は中断していましたが、昭和24年(1949)「口腔衛生週間」として復活しました。

昭和33年(1958)から「歯の衛生週間」、平成25年度(2013)「歯科口腔保健の推進に関する法律」の施行を機に現在の「歯と口の健康週間」になりました。昭和33年(1958)から厚生省(現・厚生労働省)、文部省(現・文部科学省)が、平成25年(2013)から日本学校歯科医会(にほんがっこうしかいしかい)が加わって現在のかたちで実施しています。
・歯の衛生に関する正しい知識の普及啓発
・歯科疾患の予防処置の徹底
・歯科疾患の早期発見、早期治療を励行
これらを徹底することにより、歯の寿命を延ばし、国民の健康の保持増進を目的としています。

昭和30~40年代、日本は「虫歯の洪水時代」といわれるほど「虫歯(う蝕、うしょく)」の患者が多く、町の歯科医院は虫歯の痛みで駆け込むひとであふれていましたが、現在、子どもたちの虫歯は劇的に減りました。また、平成元年(1989)から厚労省と日本歯科医師会が展開している「8020(ハチマルニイマル)運動」(80歳になっても20本以上の自分の歯を残そうという運動)の成果もあり、平成28年(2016)には2人に1人が20本以上の歯を保つようになりました。
人生100年時代を迎え、「健康寿命」をのばすことが国家的な課題となりました。そして、口の健康が全身の健康に密接に関わることが最近の研究で明らかになってきたことから、「虫歯予防デー」から始まった運動は、「歯科医療」と「口腔健康管理」の2本立ての運動へと変わってきました。

日本歯科医師会では平成27年(2015)から、従来の「8020運動」に加えて「オーラルフレイル」対策に力を入れ始めました。
「フレイル」とは、日本老年医学会が「虚弱」を意味する英語の訳語として提唱した概念で、「加齢とともに体力と気力が低下した状態」を指します。そのままフレイルを放っておくといずれは要介護になるリスクが高まり、適切に対応すれば要介護になるのを先送りすることができる、「健康」と「要介護」のはざまの状態をフレイルといいます。
「オーラルフレイル」は、「健口(口の機能の健常な状態)」と「口の機能低下」とのはざまの状態です。オーラルフレイルは、全身のフレイルや「サルコペニア(筋肉減弱)」、低栄養などを引き起こすと考えられています。噛みにくい、食べこぼしてしまう、むせる、滑舌が悪くなるなどのオーラルフレイルの症状は、全身のフレイルの兆候として顕著にあらわれるため、こうした「口の衰え」を改善することは、全身の健康状態を保つことにも繋がります。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

かつてはもっぱら虫歯の予防と治療でしたが、口腔を清潔に保ち、口腔ケアを続けることが、健康な生活を送るうえで大切なのだとわかってきました。「食べる」「話す」「笑う」といった日常生活の楽しみや喜びをできるだけ長く味わうためにも、「口の衰え」には早めに対処したいものです。
筆者敬白













