■6月1日「鮎釣り解禁」です。■
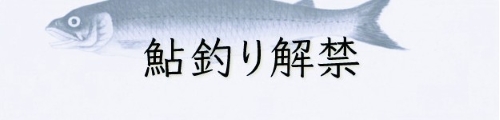
6月1日は「鮎釣り」の解禁日です。河川や湖沼などでの釣りや投網(とあみ)を「内水面漁業(ないすいめんぎょぎょう)」といいます。営利を目的としない釣り・潮干狩りなどを「遊漁(ゆうぎょ)」といい、内水面において「漁業権」の対象となる魚を釣る場合には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間などの遊漁規制が定められています。

個人でやるぶんには自由に魚釣りや潮干狩りなどができると思われがちですが、実際は、「漁業法(ぎょぎょうほう)」「水産資源保護法(すいさんしげんほごほう)」などの法律や都道府県の「漁業調整規則」「遊漁規則」など、さまざまな規制が設けられています。
山梨県・神奈川県を流れる一級河川「相模川(さがみがわ)」は、かつて「鮎川(あゆかわ)」と呼ばれたほど鮎が多く、鮎業も盛んで、江戸時代には相模川の鮎は将軍家への「献上鮎(けんじょうあゆ)」として江戸城に上納されていました。現在も、相模川は全国有数の鮎釣りポイントです。遊漁期間は、6月1日~10月14日および12月1~31日(相模川漁業協同組合連合会)。
遊漁期間も含め、釣り場によってそれぞれ決めれらた規制があります。釣り人には、遊漁料・漁法・遊漁区域などが記載された遊漁証認証を携帯すること、マナーを守って川の環境を保護すること、天候の確認やライフジャケット着用等による安全対策などが求められます。
「アユ(鮎)」は、キュウリウオ目キュウリウオ科に分類される魚。川と海を回遊(かいゆう)する魚で、日本では代表的な川釣りの対象魚であり、重要な食用魚です。優美な姿と独特の香気で知られ、中国では「香魚(シャンユイ)」と呼ばれます。

現在の「鮎」の字が当てられている由来には、神功皇后(じゅんぐうこうごう)が肥前国松浦郡の玉島川(たましまがわ)でアユを釣って戦いの勝敗を占ったとする説や、アユが一定の縄張りを独占する(占める)ところからつけられた説など諸説あります。漢字の「鮎」は奈良時代ごろから使われていましたが、当時はナマズを意味していました。アユのことは、記紀を含めてほとんどの場合、「年魚」と書かれています。
体は細長く紡錘形で、サケ(鮭)のように「脂鰭(あぶらびれ)」を持ちます。成魚は全長30cmに達しますが、地域差や個体差があります。
「若魚(わかうお)」は、全身が灰緑色で背鰭が黒、胸びれの後方に大きな黄色い楕円形の斑が1つあります。秋に性成熟すると、橙色と黒の婚姻色が発現します。背側が青緑色,腹側は色が薄く,えらぶたの後方に2つの黄色い斑紋が浮かびます。
◆生態

アユは「回遊魚(かいゆうぎょ)」です。9~12月ごろ川底に産卵。産卵後の親は死に、孵化した稚魚はすぐに海に降ります。翌春3~5月ごろ再び川を「遡上(そじょう)」して、さらに成長したのちに産卵します。このようなライフサイクルを「両側回遊(りょうそくかいゆう)」といいます。
「鮎」は夏の季語ですが、アユの一生の移り変わりがそれぞれの季節と結びついて季語になっています。「若鮎」は春の季語。産卵のため下流へ向かって川を下り始めることを「落ち鮎(おちあゆ)」と呼び、これは秋の季語。体が半透明で体長3~4cm程度の稚魚を「氷魚(ひうお、ひお)」といい、冬の季語になっています。
琵琶湖などの「コアユ」は、海の代わりに湖で成長し、一部は川へ溯上、大部分はそのまま湖で成魚となります。湖で育つと10cmほどの小型の成魚になります。
◆漁法

アユ漁には、投網(とあみ)や建網(たてあみ)、梁(やな)などの漁具を用います。
「鮎の友釣り(ともづり)」――アユの若魚は、川底の石や岩に付着した藻類を食べて成長します。このとき良質な藻類を確保するため、自分の「縄張り」をつくり、そこへ入ってきた他のアユに体当たりするなどして追い払います。アユのこの性質を利用して、おとりアユを縄張り域に近づけ、攻撃してくるアユを針に引っ掛けて釣り上げるのを「友釣り」といいます。
「鵜飼い(うかい)」――飼いならした鵜(う)を使ってアユなどを獲る伝統的な漁法です。平底の小船の舳先でかがり火が焚かれ、その光に驚いて活発になったアユは、うろこが光に反射して鵜に捕らえられます。岐阜の「長良川鵜飼(ながらがわうかい)」「小瀬鵜飼(おぜうかい)」は、宮内庁式部職(しきぶしょく)である鵜匠(うしょう・うじょう)によって行なわれます。特に宮内庁の御料場(ごりょうば)で獲れたアユは皇居へ献上されます。
◆料理

アユの旬は、もっとも脂の乗る7~8月です。秋になり産卵のため川を降りる子持ちアユも賞美されます。また、若いアユには、「香魚」の名にふさわしく、スイカやウリに似た香りがあります。水質の良い川の中流域にアユが集まり密度が高くなると、川原がアユの芳香で満たされることがあります。
アユといえば「塩焼き」です。表面を焦がさずに加熱するため、ぴんと尾をはねた姿に金串を打ち、鰭(ひれ)に化粧塩をして焼きます。泳いでいるときのように体をうねらせて串を打つので、「登り串(のぼりぐし)」や「うねり打ち」などといいます。
塩焼きのほかに、てんぷらやフライ、魚田(ぎょでん:味噌田楽)、煮びたしなどの料理法があります。また、アユの内蔵を塩漬けにして熟成させた塩辛を「うるか」といって珍味のひとつです。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆
鮎釣りが解禁されたというニュースを聞くと、夏が近づいてきたと感じます。しかしそのまえに暦の上ではまもなく「入梅」、ジメジメした季節に入ります。菌が繁殖しやすい時期でもありす。食中毒にはくれぐれもご注意を。
筆者敬白













