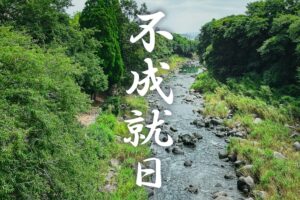■4月29日~5月5日「有田陶器市(ありたとうきいち)」です。■
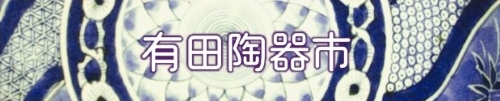
毎年ゴールデンウィークの期間に佐賀県有田町(ありたちょう)で「有田陶器市(ありたとうきいち)」が開催されます。九州を中心に、全国から約120万人の人出で賑わいます。

「有田焼(ありたやき)」は、佐賀県有田町を中心とする地域で、江戸時代初期から焼き続けられている磁器です。佐賀県北西部にある伊万里港(いまりこう)から積み出されたので「伊万里焼(いまりやき)」とも呼ばれます。
文禄・慶長の役(1592-98)で。朝鮮へ出兵した佐賀藩主鍋島直茂(なべしまなおしげ)が連れ帰った朝鮮人のなかに陶工「李参平(りさんぺい)」がいました。李は有田町泉山に白磁鉱を発見し、初めて磁器の焼造を始めたと伝わります。新技術による磁器生産は、「オランダ東印度会社」が大量に買い付けたことも後押しとなり、肥前鍋島の重要産業として急成長しました。

事業参加のために訪日していたドイツの化学者「ゴットフリード・ワグネル」博士は、明治3年(1870)有田に滞在し、陶磁器に関する窯や焼成法、釉(うわぐすり)、七宝(しっぽう)、石膏などの使用法など、多くの欧州の技術を伝えました。そのひとつが石炭窯です。それまでは山の斜面に窯を築き、薪で焚く登窯(のぼりがま)で焼成されていましたが、石炭を使って平地で焼く石炭窯が日本で初めて有田で築かれました。石炭窯は燃料(薪)不足の問題を解消し、明治後期になって国内に普及しました。
また、ワグネル博士は絵具の改良にも貢献しました。それまで有田焼に見られる藍色の文様は「呉須(ごす)」と呼ばれる中国の天然鉱物を使っていましたが、工業的に製造された「コバルト」という絵具の使用法を教えました。コバルトは呉須よりも安価で、鮮やかに発色し、自由に濃淡が調節できました。

明治29年(1896)、香蘭社(こうらんしゃ:明治7年設立の有田の磁器工場)社長・深川栄左衛門(ふかがわえいざえもん)と、有田磁器窯業組合の組合長・田代呈一(たしろていいち)が主催し、有田町の桂雲寺で最初の「陶磁器品評会」が開かれました。その後、大正4年(1915)の陶磁器品評会の協賛行事として行なわれた「蔵ざらえ大売出し」が「有田陶器市」の始まりです。
戦前は品評会が主でしたが、今では陶器市が盛んになり、現在の「有田陶器市」に発展しました。町内約4kmにわたって有田焼の店など約700軒が並び、日本全国から120万人を越える人が訪れる規模となっています。
◆「有田陶器市」公式サイト:https://www.arita-toukiichi.or.jp
◇開催地:佐賀県西松浦郡有田町
◇最寄り駅:JR九州「有田駅」「上有田駅」
◇期間中、臨時列車「有田陶器市号」特急「有田陶器市みどり号」など運転
◇西九州自動車道「波佐見有田IC」すぐ