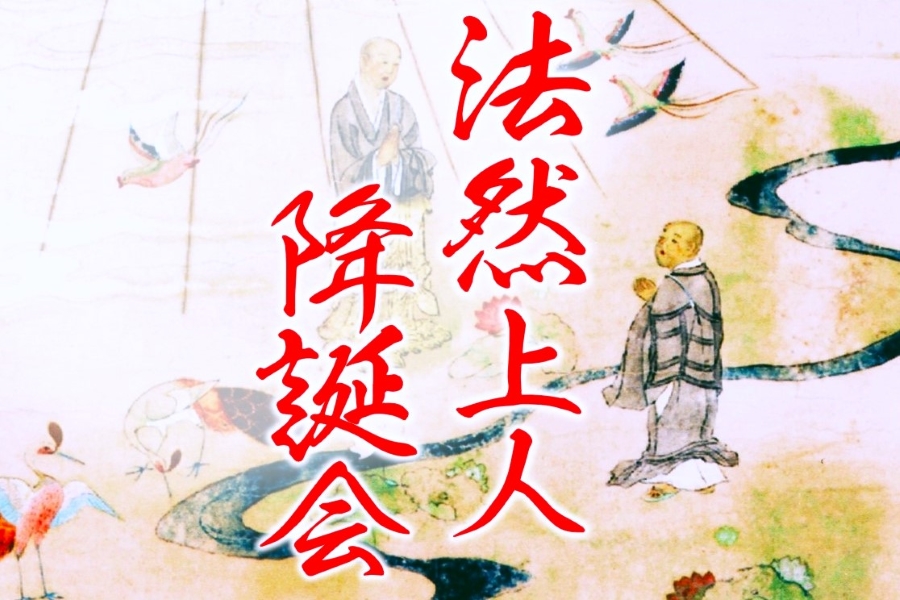■4月7日「法然上人降誕会(ほうねんしょうにんごうたんえ)」です。■
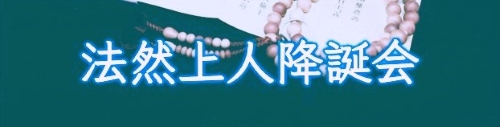
「法然上人(ほうねんしょうにん)」は、平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の僧侶で「浄土宗(じょうどしゅう)」の開祖。真宗七高僧の第七祖。円光大師(えんこうだいし)、「法然」は房号(ぼうごう)で、諱(いみな)は源空。幼名は勢至丸(せいしまる)。

長承2年(1133)4月7日、美作国久米南条稲岡庄(現在の岡山県久米郡久米南町)の押領使(おうりょうし)・漆間時国(うるまときくに)と、母・秦氏君(はたうじきみ)とのあいだに誕生。夫婦には子どもがなかったので観音様に一心込めて子を授からんことを願い、やがて4月7日玉のような男の子を賜ります。
誕生の時、空から二流(ふたながれ)の白幡が舞い降りて屋敷内の椋(むく)の木の梢にかかり7日の後に飛び去ったと伝わります。「二幡の椋(ふたはたのむく)」「誕生椋(たんじょうむく)」と呼ばれます。
保延7年(1141)、9歳の時、漆間家は突然、明石源内定明(あかしげんないさだあきら)の夜襲を受け父を失いますが、仇として定明を追うことを戒めたうえに「仏道を歩み安らぎの世を求めよ」との父の遺言にしたがって仇討ちを断念。
母の弟・観覚(かんがく)得業上人に引き取られ、15歳の時に比叡山の皇円(こうえん)について得度。比叡山黒谷の叡空(えいくう)に師事します。
「法然」という房号は、叡空が「法然道理の聖(ひじり)」であると評価したことから得たといわれています。「法然道理」とは、物事の動かしようのないあるがままのすがたという道理のこと。また、師の「源光」と「叡空」から一字ずつ取り「源空」という諱を授けました。以降、「法然房源空」と名乗ります。18歳の頃には多くの経典を読破し、優秀な学僧として将来を嘱望されるようになります。

承安5年(1175)、43歳の時、善導(ぜんどう、光明大師)の教義書『観無量寿経疏(かんむりょうじゅきょうしょ)』によって「専修念仏(せんじゅねんぶつ)」に進み、比叡山を下って東山吉水(よしみず)に住み、念仏の教えを広めました。この年を浄土宗の立教開宗の年としています。
文治2年(1186)大原勝林院(おおはらしょうりんいん)で聖浄二門(しょうじょうにもん)を論じ(大原問答)、建久9年(1198)『選択本願念仏集(せんちゃくほんがんねんぶつしゅう)』(略称『選択集(せんちゃくしゅう)』)を著します。

法然は特に中国の善導の思想を重視しました。それは「極楽浄土への往生を一心に願い、常に念仏をしていれば、必ず阿弥陀仏がその者を救ってくれる」という思想でした。法然の教えは、そのわかりやすさから多くの人々の帰依を受けることになります。しかし、これは既成の仏教教団にとっては非常に危険な思想でもありました。そのため、法然と弟子たちは激しい弾圧を受けたのです。
元久元年(1204)、比叡山の僧徒が専修念仏の停止を迫って蜂起。法然は「七箇条制誡(しちかじょうせいかい)」を草して門弟190名の署名を添え延暦寺に送りましたが、興福寺の奏状により念仏停止の断が下されました。
建永2年(承元元年・1207)、法然は還俗させられ、「藤井元彦」の名前で土佐国(讃岐国)へ流罪となりました。この「建永の法難(承元の法難)」では、ふたりの弟子が死罪になり、法然と数名の弟子が各地に流罪になりました。しかしこれが結果的に浄土系仏教を全国に広めることになるのです。
4年後の建暦元年(1211)、赦免になり帰京。翌年1月25日死去。享年80歳。1月23日に源智(げんち、勢観房)の願いに応じて遺言書「一枚起請文(いちまいきしょうもん)」を記しています。
法然の門下に、證空・源智・弁長・幸西・親鸞・長西らがいます。俗人の帰依者、庇護者として、九条(藤原)兼実、熊谷直実、宇都宮頼綱らが知られます。
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

浄土宗の寺院では、4月7日の「宗祖降誕会(法然上人の誕生を祝し報恩謝徳を表す法会)」を翌8日の「灌仏会(かんぶつえ:釈尊の誕生を祝う法会)」と合わせて執り行なわれることが多いようです。宗祖降誕会では「二幡の椋」の奇瑞(きずい:不思議な出来事)にもとづいて、白い2本の仏幡を掲げて荘厳し法然上人の誕生を祝います。
4月に入り、過ごしやすい季節になりました。
花見に興じて夜風にあたりお風邪などお召しにならないよう
お体ご自愛専一の程
筆者敬白