■3月13日 奈良、春日大社「春日祭(かすがさい)」です。■
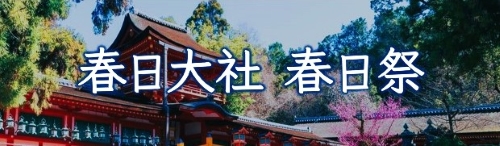
「春日大社(かすがたいしゃ)」は、「奈良公園」内にある神社で、名神大社式内社、二十二社の一社、旧社格は官幣大社。全国の春日神社(かすがじんじゃ)の総本社です。神山である「御蓋山(みかさやま:春日山)」の麓に、奈良時代の神護景雲2年(768)、称徳天皇(しょうとくてんのう)の勅命により「平城京の守護」として創建されました。

本殿向って右から、
第一殿に茨城県の鹿島神宮から迎えた「武甕槌命(たけみかづちのみこと)」、
第二殿に千葉県の香取神宮から迎えた「経津主命(ふつぬしのみこと)」、
第三殿に「天児屋根命(あめのこやねのみこと)」、
第四殿に「比売神(ひめがみ)」は大阪府枚岡神社(ひらおかじんじゃ)から、
それぞれ春日の地に迎えて祀られています。
四神をもって藤原氏の氏神とされ、「春日神(かすがのかみ)」と総称されます。「春日明神」「春日権現」とも。

また、武甕槌命が白鹿に乗ってやってきたとされることから、「鹿」は春日明神の神使(しんし:かみのつかい)「神鹿(しんろく)」として大切にされてきました。
奈良公園にはおよそ1100頭の鹿がいます(令和3年現在)。『万葉集』にも「春日野に粟蒔けりせば鹿待ちに継ぎて行かましを社し怨む(春日野に粟を蒔いたら、粟を食べに来る鹿を待ち続けるように通い続けましょうものを。神の社があるのがうらめしいことです)」(佐伯赤麻呂)と読まれているように、昔から鹿が生息していました。奈良公園の鹿は飼育されていない野生生物で、国の天然記念物に指定されています。

奈良公園の東に位置する「春日山原始林(かすがやまげんしりん)」は、市街地に隣接する貴重な照葉樹林の原始林で、国の特別天然記念物に指定されています。1100年以上前に狩猟と伐採が禁止されて以来、春日大社の聖域として守られてきました。春日大社で行なわれる多くの神事には、春日山原始林のなかで古代の神事さながらに執り行われるものもあり、春日山原始林が春日大社と一体となって古くからの信仰を伝えていることがわかります。こうしたことから、春日山原始林も春日大社とともに「古都奈良の文化財」を構成する文化遺産として世界遺産に登録されました。
◆春日祭(かすがさい、かすがまつり)
「春日祭」は嘉祥2年(849)に始まったと伝えられ、葵祭(あおいまつり)、石清水祭(いわしみずさい)とともに「三勅祭」〔※〕のひとつといわれます。午前9時、天皇陛下のご名代である勅使を迎えて、国家の安泰と国民の繁栄を祈ります。

明治19年(1886)の旧儀再興で例祭日が3月13日に定められた例大祭です。明治維新以前は年2回、旧暦2月と11月の申の日(さるのひ)が祭祀日だったことから「申祭(さるまつり)」とも呼ばれています。

※勅祭(ちょくさい):勅命によって勅使を差遣し、奉幣(ほうへい)を行なう祭。これを受ける神社を「勅祭社(ちょくさいしゃ)」という。勅祭は法に基づいて定められるのではなく、天皇の思し召しによって行われる。勅祭の特徴は、勅使による幣帛(へいはく)奉献が行われること。「幣帛」とは、神に奉献するものの総称で、「幣物(へいもつ)」「みてぐら」「にきて」「ぬさ」ともいう。
三勅祭、三大勅祭
・春日祭(奈良市、春日大社)
・葵祭(京都市、上賀茂神社・下鴨神社)
・石清水祭(京都府八幡市、石清水八幡宮)
春日大社
◇奈良県奈良市春日野町160
◇バス「春日大社本殿」下車、または「春日大社表参道」徒歩10分
◇公式サイト:https://www.kasugataisha.or.jp
◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆

春日大社の祭事を調べていて、明治維新で祭祀が中断された歴史があることを知りました。そもそも春日大社は藤原氏の氏神であることから、藤原氏の氏長者(うじのちょうじゃ:氏のなかの代表者)が祭祀を行なっていました。藤原氏の隆盛とともに祭りも壮麗になりましたが、応仁の乱以降は中絶。元禄年間に略式化したかたちで再興され、明治19年(1886)、旧儀復興して再び勅祭となりました。
歴史の転換点には、今までの文化・習慣が否定された史実を見つめましょう。新しいものが流行ると、それまでのものが中断や廃止に追い込まれる文化は、どこか未熟さを感じます。
現在の春日祭は平安時代の祭祀の姿をよくとどめているとのこと。どのようなものであれ、次の世代に引き継ぐ努力を欠かさない歴史観が大切です。
3月の中旬、季節の変わり目です。
時節柄お体ご自愛専一の程
筆者敬白













